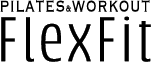ストレス社会の処方箋にピラティス:“動く瞑想”という選択
2022年11月21日公開(2025年7月24日更新)

忙しい仕事、終わりの見えない家事、育児のプレッシャー―現代の私たちは常にストレスにさらされています。多少のストレスは自然なことですし、個々の課題へ立ち向かうために必要なものですが、過度なストレスの中で無理をし過ぎると免疫力が低下して体調を崩しやすくなります。肩や首の張りが取れない、寝つきが悪い、気分が沈むといった不調は、心だけでなく身体の姿勢や呼吸までも巻き込みながら悪循環をつくります。こうしたループを断ち切る方法として近年注目されているのが“動く瞑想”とも言われるピラティスです。姿勢改善やボディメイクのイメージが先行しがちですが、実は呼吸法・滑らかな動き・体幹の安定を組み合わせることで、自律神経に働きかけメンタル面まで整えるエクササイズとして支持を集めています。今回はピラティスの心を再起動させてストレスを解消するメカニズムを深掘りします。
ストレスが心身に及ぼす3つの負の連鎖
ストレス反応は脳で生まれ、自律神経・ホルモン・筋肉・睡眠へと一気に波及します。まずはこの連鎖を可視化し、「なぜ身体を動かすケアが必要なのか」を整理しましょう。
自律神経の乱れとホルモンバランス崩壊

朝から夜まで気を張りつめる生活が続くと、交感神経が優位になりっぱなしになり、心拍数や血圧が高止まりします。並行してストレスホルモンであるコルチゾールが大量に分泌され、血糖や脂質の代謝が乱れるため、疲労感・集中力低下・体重増加などの不調が現れます。副交感神経を優位に切り替えるスイッチが押せない限り、この過剰警戒モードは続き、慢性的なだるさとイライラを生み続けることになります。
筋緊張・血流不良が引き起こす肩こり・頭痛・倦怠感

長時間のデスクワークやスマホ操作は、背骨の動きを硬くし、肩や首などの筋肉を過度に緊張させます。こうした筋肉が硬くなると血流が阻害され、乳酸など疲労物質が蓄積し、さらなる痛みを呼び込みます。骨盤と背骨が前後左右にアンバランスになることで、体幹のコアマッスルが正しく働かず、身体全体の安定性が低下します。身体の不安定さへの警戒がストレス反応を強めてしまい、また不調を起こす…そんな負のスパイラルが生まれます。
ピラティスの肩凝り改善効果、腰痛改善効果についてそれぞれチェック!
睡眠の質低下がメンタル不調を増幅

張り詰めた精神状態などで交感神経優位が続くと、夜になっても脳が高回転のままとなります。こうなると寝つきが悪く、眠っても浅いレム睡眠が増えるため、成長ホルモン分泌や身体修復が不十分になります。回復しきれない身体では翌日もストレスを処理する余力が足りず、不安や抑うつ感が強まりやすくなります。この睡眠負債は自律神経をさらに乱し、身体と心のダブルダメージへと発展します。
呼吸と動きがもたらす“自律神経リセット”
ピラティス最大の特徴は「呼吸と動きを同期させながら体幹を安定させる」点です。この同調が自律神経にどのような影響を与えるのかを紐解きます。
そもそも自律神経とは?
人間の身体にあるたくさんの神経の一つで内臓や代謝、体温といった身体の働きの調整をしてくれる神経です。その中でも心と身体を活発に動かす「交感神経」と、逆にリラックスして休ませる「副交感神経」がバランスを取りながら、ONとOFFの状態を切り替える様な働きをしています。この二つのバランスがうまく取れないと自律神経が乱れた状態となり、心身に支障をきたしてきます。
深いラテラル呼吸が副交感神経を優位に導く

ピラティスでは肋骨を横方向に大きく広げ、横隔膜を上下に動かすラテラル呼吸を行います。吸気で肺底部まで酸素が行き渡り、横隔膜のリズミカルな動きが迷走神経を刺激します。これは副交感神経のスイッチであり、心拍数と血圧を穏やかに整えます。深い呼吸により一酸化窒素が血管内皮から放出されると血管拡張が起こり、脳への酸素供給が改善されます。結果として安心感とクリアな思考が生まれ、ストレスを感じると分泌が増えるホルモンであるコルチゾール値も低下すると言われています。レッスン後にスッキリした充実感に溢れた気持ちになるのはこうした呼吸の効果もあるでしょう。
「フロー」が血流を促しストレスホルモンを低減

ピラティスの大切な原則の一つ、「フロー(Flow)」は動きから動きへと滑らかに移行していくことで、筋肉や関節の協調性を高めながら、身体に負担をかけにくい動作を目指すアプローチです。しなやかな身体を作るためにゆったりと、そして呼吸や動きへの集中をしながら行う動きが多いため、激しい運動をした時のようなストレスが少なく心地よさを感じられます。
胸椎の伸展や骨盤ニュートラルポジションを保ちつつ四肢を大きく動かすことで、静脈還流が促進され、全身の血液循環が活性化します。筋ポンプ作用により老廃物が流されるため、ストレス由来の筋肉痛やだるさの軽減につながります。さらに、一定リズムで呼吸と動きをリンクさせることは自律神経が制御され、交感神経の過剰な興奮を抑えます。また、特に背骨を意識する動きが多く、背骨を重点的に動かし姿勢を改善していくため、背骨の中の神経や髄液を刺激し、自律神経を整える効果も期待されます。
姿勢改善が脳血流とホルモン産生をサポート

ピラティスの効果によって猫背など不良姿勢が修正されて胸郭が拡がると、脳へ送られる血流量がアップし、ホルモンバランスを司る視床下部や脳下垂体にも十分な酸素と栄養が届きます。また、体幹が安定すると呼吸に関わる筋肉の過緊張が緩み、呼吸効率が向上します。結果として全身の細胞がエネルギーを円滑に産生でき、ストレス耐性が底上げされます。
集中・身体感覚・インナーマッスル強化で“こころのタフネス”を育む
呼吸と動きに続いて、ピラティスが重視する「集中」と「体幹の安定」はメンタル面へどのように作用するのでしょうか。
集中とボディスキャンが雑念を遮断

ピラティスでは一つ一つの動きを行う際、骨盤の位置、胸郭の開閉、肩甲骨の滑りなど細かな部位感覚に意識を向けます。この“動くボディスキャン”は過去や未来の不安ではなく「今この瞬間」に注意を集中させる訓練です。雑念を遮断することで脳の感情や記憶の処理に関わる神経細胞「扁桃体」の過剰活動が鎮まり、心理的ストレス反応が弱まります。
インナーマッスル強化が心理的安定感をもたらす

ピラティスが重視するコアマッスル(多裂筋・腹横筋・骨盤底筋群・横隔膜)を中心に鍛えることで、背骨と骨盤が安定し、身体の“芯”が通ります。こうして体幹が安定し正しい姿勢を無理なく取れるようになると身体の緊張が和らぎます。さらに正しい姿勢は自信を持った行動につながるため、積極性・自己効力感が高まると言われています。つまり物理的な重心安定が精神的な安定感へと投影されると言えます。
ピラティスでインナーマッスルを鍛えることで身体が整う効果とは?
小さな成功体験がセルフイメージを向上

ピラティスは身体の微細な動きをコントロールするエクササイズです。回を重ねるごとに「できなかった動作ができる」「呼吸が深まった」といった小さな成功体験が積み重なります。こうした達成感は幸せホルモンであるドーパミンの分泌を促し、前向きな感情を強化します。こうして自己肯定感が高まることでストレス耐性も同時に育まれます。
まとめ
ストレスは自律神経の乱れから筋緊張、睡眠障害、メンタル不調へと連鎖しますが、ピラティスはラテラル呼吸・滑らかな動き・集中力・体幹安定という4本柱でこの連鎖を断ち切ります。副交感神経を優位に戻し、血流を改善し、自己効力感を高めることで、身体だけでなく心にも働きかけるエクササイズです。今日から深い呼吸を意識し、少しずつ動きを取り入れてみてください。身体が整えば心も整い、ストレスに揺らぎにくいタフな自分に近づけます。
ストレス解消にもピラティス!まずはFlexFitピラティス・ワークアウトで体験を申し込む!
公式インスタグラム( @flexfit_pilates_workout )では様々なエクササイズ、ピラティスの効果などを公開中!