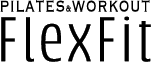ピラティス呼吸法完全ガイド|身体と心への効果と正しいやり方
2023年1月28日公開(2025年10月31日更新)

ピラティスの基礎でありながら、最も奥が深いのが「呼吸法」です。呼吸は身体の動きをコントロールし、心の状態までも左右します。ピラティスにおける呼吸は、単なる酸素の出し入れではありません。呼吸は動作のリズムを導き、身体を安定させ、心を落ち着かせる重要な要素です。呼吸を疎かにすると体幹が安定せず、動作の質も安全性も大きく低下します。そして呼吸は姿勢や集中力の改善、疲れにくい身体づくりに大きな影響を与えます。今回はピラティスの呼吸法の理論・メカニズム・効果・実践法を包括的に解説します。呼吸を正しく使えるようになると、動作の質そのものが根本から変わっていくことに気づくはずです。
ピラティスで呼吸が最重要とされる理由
ピラティスの創始者であるJ.H.ピラティス氏は“Above all, learn how to breathe correctly.“(何よりも、正しく呼吸する方法を学びましょう)と述べており、「呼吸」はピラティスの基本原理・原則の一つです。これは呼吸が姿勢保持と動作精度を同時に司る“司令塔”となっているからです。まずはピラティスにおける呼吸の働きを見ていきましょう。
呼吸が動作の精度を高めるメカニズム

ピラティスでは「呼吸と動作の同調」が何より大切です。息を吸うタイミングで胸郭が広がり、吐くタイミングで体幹が引き締まります。このリズムが自然と身体の動きを導き、筋肉を最適な順序で働かせます。呼吸と動きが噛み合うことで、フォームのブレや余計な力みが減少。動作の精度が高まり、関節や筋肉への負担も軽くなります。呼吸が整うことで、動作の流れがスムーズになり、全身がひとつのリズムで連動するようになります。それはまさに、身体が「内側から導かれている」感覚です。
呼吸が脳と身体をつなぐ

深い呼吸は、脳への酸素供給を増やし、集中力と感覚の鋭さを高めます。身体に酸素が十分に循環すると大脳皮質が活性化し、固有受容感覚(自分の身体が今どの位置にあるか、どの程度の力が入っているか、関節がどのような状態にあるか、などを脳が正確に把握するための感覚)が鋭敏になります。
ピラティスでは動きや身体の状態を常に意識するため、正しい呼吸はこの固有受容感覚をサポートします。逆に浅い呼吸では身体の緊張が抜けず、動きも雑になりがちです。そのため深く一定の呼吸を意識することで、脳と身体の連携がスムーズになり、リズミカルで安定した動作が可能になります。意識的な呼吸は、神経系の働きを整え、脳の過剰な興奮を鎮める作用も持っています。思考が静まり、身体の声を自然に感じ取れるようになります。
安全なエクササイズの土台をつくる

正しい呼吸は、ピラティスを安全に行うための土台でもあります。息を止めると腹内圧が急上昇し、脊柱や関節に過剰な負荷をかける原因になります。呼吸を続けることで体幹が内側から“コルセット”のようになって脊柱を支えるので、腰や首の安定性が保たれます。また、呼吸に意識を向けることで動作スピードが自然とコントロールされ、ケガの予防にもつながります。呼吸が整っていると、エクササイズ中の筋肉の働きが均等になり、左右差の改善にも効果的です。正しい呼吸は、しなやかで持続的に動ける身体をつくる第一歩なのです。
胸式ラテラル呼吸とは?そのメカニズムと実践のコツ
ピラティスの代表的な呼吸法である「胸式ラテラル呼吸」は、「ラテラル(Lateral)」=横からの、側面の、水平の、という言葉の通り、胸郭(心臓や肺などを守る胸部の肋骨、胸骨、胸椎のこと)を横方向(側面と背面)に広げるようにして行う呼吸法です。
通常呼吸との違い

一般的な腹式呼吸はリラックス効果に優れていますが、ピラティスには適しません。ピラティスでは、体幹の安定を保ちつつ酸素を取り込む「胸式ラテラル呼吸」を採用します。これは胸郭を横に広げて行う呼吸で、腹部を膨らませずに呼吸筋を効率よく働かせる方法です。動作中も体幹の緊張を維持できるため、姿勢が崩れず動作の軸が保たれます。胸郭の可動性を高めることで、背中全体が柔軟に動き、より深い呼吸が可能になります。横隔膜を制御する感覚を養うことが、安定した動作につながります。
呼吸筋群の役割

ピラティスの呼吸では、横隔膜・肋間筋・腹横筋といった“呼吸筋群”が密接に連動します。息を吸うと横隔膜が下がり、肋骨が外側に広がります。同時に腹横筋が内側から支えて体幹の安定を保ちます。息を吐くときにはこれらの筋群が収縮し、余分な空気をしっかりと押し出します。このように、呼吸そのものが体幹トレーニングの一部となります。筋肉が連鎖的に働くことで、呼吸が滑らかになり、姿勢が自然と整っていきます。こうした呼吸筋の協調性はピラティスの根幹です。
胸式ラテラル呼吸を行うコツ

胸式ラテラル呼吸は鼻から息を吸いますが、この時肩を上げたり首の筋肉を使わず、肩甲骨の動きとともに胸郭を左右に大きく広げるイメージで行います。名前に「胸」とつくため胸の前側を意識しがちですが、実際は背中側、特に肋骨の背面まで膨らませるように吸気を行います。吸う際、横隔膜が下降することで本来は腹部が前方に膨らみやすくなりますが、この呼吸では腹横筋が“天然のベルト”のように腹部を引き締めているため、お腹を膨らませずに胸郭を外側と背面に広げることができます。これにより、吸気中であっても体幹が安定した状態を保つことが可能です。
そして吐くときは、胸郭がゆっくりと閉じていくのを感じながら、口から細く長く息を吐き出します。呼気時には横隔膜が上昇し、同時に腹横筋の働きが強まり、骨盤底筋群と連動して体幹がシリンダーのように安定します。こうした呼吸のメカニズムによって、ピラティス中の動作において体幹の安定性と力の伝達効率が高まり、より安全かつ効果的なエクササイズを実現することができるのです。
ピラティス呼吸がもたらす身体への効果
呼吸は目には見えませんが全身を支える“基礎筋トレ”とも言えます。意識して行う呼吸こそ、最も効果的なエクササイズの一つです。
体幹強化と姿勢改善

呼吸を通して体幹のインナーマッスル(特にコアマッスルと呼ばれる腹横筋・多裂筋・横隔膜・骨盤底筋群)が働くことで、自然に体幹が安定します。これらの筋肉は「姿勢保持筋」とも呼ばれ、呼吸とともに使うことで本来の機能を取り戻します。呼吸を意識するうちに、肩が下がり、背筋がすっと伸びる感覚が得られるでしょう。体幹が整うことで、動作の支点が安定し、全身のエネルギー効率も向上します。つまり、正しい呼吸は姿勢を「作り直す」ための最も自然なトレーニングなのです。
ピラティスの姿勢改善効果と体幹強化の効果についてそれぞれをチェック!
血流・代謝アップと疲労回復

深い呼吸は胸郭を大きく動かし、全身の血流を促進します。これにより酸素がすみずみまで行き渡り、代謝が活性化します。老廃物の排出もスムーズになり、疲れにくく、むくみにくい身体へと導きます。特にデスクワークなどで呼吸が浅くなりがちな人ほど、この効果を実感しやすいでしょう。呼吸を深めることは、血液循環を“内側から整えるマッサージ”のようなものです。身体の隅々まで新しい空気が行き渡る感覚を大切にしましょう。
呼吸筋のトレーニング効果

ピラティスの呼吸は、肺を動かす筋肉を鍛える“呼吸筋トレーニング”でもあります。日常の呼吸では使われにくい肋間筋や横隔膜の可動性を高めることで、呼吸の深さが増し、持久力が向上します。継続することで、階段を上るときの息切れや慢性的な疲労感が軽減される人も多いです。呼吸を意識することで、筋肉の働きがより統合的になり、エネルギー消費の効率も上がります。まさに呼吸こそが、全身のパフォーマンスを底上げする鍵なのです。
ちょっと休憩
ピラティスの創始者、J.H.ピラティス氏は動物好きとしても知られ、猫のしなやかな呼吸と動きを長時間観察してこのメソッドのヒントを得たそうです。胸郭と骨盤を連動させた“しなやかさ”こそが彼の目指した理想の身体だったそうです。
心を整える呼吸法:自律神経とマインドの安定
ピラティスの呼吸は、身体を動かすだけでなく“心の筋トレ”でもあります。呼吸を整えることで、気持ちまで安定していきます。
吸う・吐くのリズムがもたらすリラクゼーション

吸気の際は交感神経が、呼気の際は副交感神経が優位になります。このリズムを利用して、緊張とリラックスのバランスをとるのがピラティス呼吸の特徴です。吸うときに胸を開き、吐くときに力を手放す。その繰り返しが、心拍を落ち着かせ、心身を安定へ導きます。呼吸を丁寧に繰り返すことで、体内の酸素濃度と心拍のリズムが整い、自然と落ち着きが生まれます。呼吸のリズムが整うと、感情の波も穏やかになります。
マインドフルネスとの共通点

ピラティス呼吸は、瞑想やマインドフルネスと通じる部分があります。それは「今この瞬間」に意識を集中させること。呼吸を観察しながら動くことで、思考が未来や過去にさまようのを防ぎます。動きの中で呼吸を感じると、感情の波も自然に落ち着き、穏やかな心の状態が保てます。呼吸を通じた集中は、脳内のストレスホルモンを抑制する効果もあり、精神的な安定をサポートします。まさに呼吸は、心のメンテナンスそのものです。
ストレス軽減と睡眠の質向上

ピラティス呼吸は、ストレスケアにも効果的です。深くゆったりとした呼吸は副交感神経を刺激し、心拍数を下げ、筋肉の緊張を解きほぐします。その結果、睡眠の質が向上し、朝の目覚めも軽やかになります。呼吸が浅いと、心も浅く揺れやすいもの。日中に数回、意識的に呼吸を整えるだけで、ストレス耐性が高まり、感情のコントロールがしやすくなります。呼吸を整える習慣が、心のバランスを支える支柱になります。
日常に活かすピラティス呼吸:実践と習慣化のヒント
ピラティスを行っていない日常生活のあらゆる場面においても、スタジオで学んだ呼吸を意識することで、心身の調子が安定してきます。
デスクワーク中にできる呼吸リセット

長時間のパソコン作業は、姿勢を崩し、呼吸を浅くします。そんなときは椅子に深く座り、背中を伸ばして数回深呼吸。肩を後ろに引き、肋骨を広げる意識を持つだけで、呼吸が胸に入りやすくなります。わずか1分でも、頭がすっきりし、集中力が回復します。姿勢と呼吸を意識することが、身体の“リセットボタン”となります。定期的に呼吸を整える習慣をつくることで、疲労の蓄積も防げます。
睡眠前のリラックス呼吸

就寝前の数分間、仰向けになり、両手を肋骨の上に置いて呼吸してみましょう。吸うたびに肋骨が横に広がり、吐くたびに身体が沈む感覚を味わいます。このとき、口をすぼめてゆっくりと息を吐くのがポイント。副交感神経が働き、心拍が安定し、自然と眠りに入りやすくなります。呼吸の深さに意識を向けるだけでも、1日の緊張が解け、心身が休息モードへと切り替わります。静かな時間をつくることが睡眠の質を高めます。
呼吸を意識することで生まれる生活の変化

ピラティス呼吸を日常に取り入れると、姿勢が整い、感情も安定していきます。呼吸が深くなると、心にゆとりが生まれ、焦りや不安に飲み込まれにくくなります。朝の通勤中や歩行時に意識するだけでも、気分がリセットされるのを実感できるはずです。日常における「呼吸の質」は、人生の質と直結します。意識して呼吸を整える習慣こそ、健やかさを維持する最良のセルフケアです。
まとめ
ピラティス呼吸は、身体と心を同時に整える最もシンプルで効果的なメソッドです。動きと呼吸を一致させることで、体幹が鍛えられ、姿勢が整い、集中力と穏やかさが生まれます。正しい呼吸は特別な技術ではなく、「今この瞬間」を丁寧に感じること。1日に数回の意識的な呼吸が、日常を変える第一歩になります。 正しい呼吸を習慣化し、身体と心のパフォーマンスを最大化しましょう。
正しい呼吸法は丁寧な指導で身につけよう!まずはFlexFitピラティス・ワークアウトで体験を申し込む!
公式インスタグラム( @flexfit_pilates_workout )では様々なエクササイズ、ピラティスの効果などを公開中!